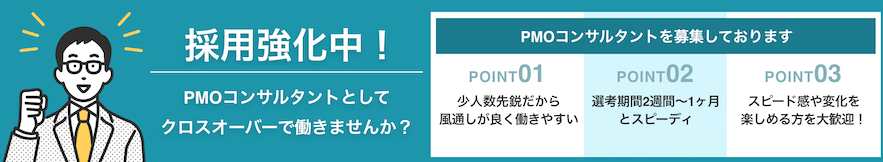- ホーム>
- ITコンサルティング>
- システム開発 PMO>
- PMOとは?プロジェクトでの役割や導入事例について分かりやすく解説
公開日:2021.10.08(金) 更新日:
プロジェクト成功率が飛躍的に上がるPMOとは?
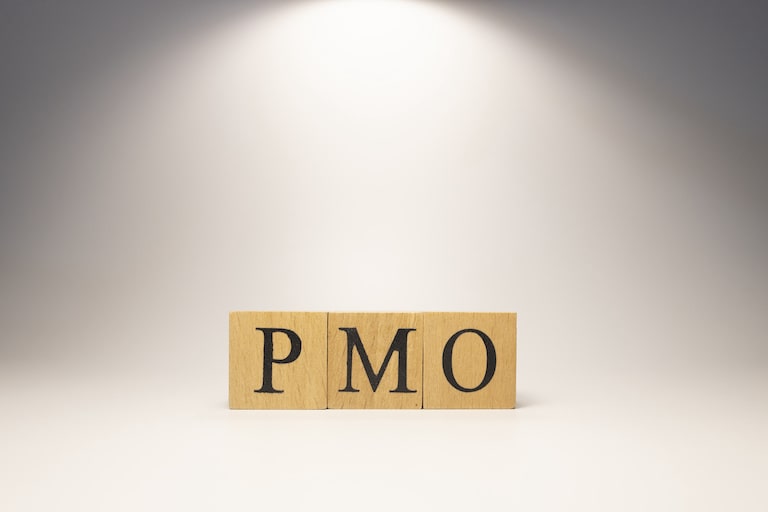
近年、企業のプロジェクトは複雑化・大規模化し、従来の「プロジェクトマネージャー個人の経験やスキル」だけでは成功に導くことが難しくなっています。
そんな中で注目されているのが PMO(Project Management Office) です。
「PMOとはそもそも何をする組織なのか?」
「プロジェクトマネージャーとの違いは?」
「導入することで本当に成果が出るのか?」
こうした疑問を抱える方は少なくありません。
この記事では、PMOの基本的な定義から役割、導入のメリット・デメリット、さらに実際の活用事例までをわかりやすく解説します。
PMOとは?

PMOとは、プロジェクトマネジメントオフィス(PMO: Project Management Office)の略で、プロジェクトマネジメントの支援する役割にあります。
直訳すると「プロジェクト管理のためのオフィス」ですが、単なる事務局ではなく、プロジェクトを成功に導くための仕組みづくりと標準化を担います。
従来はプロジェクトマネージャー(PM)が個別に管理していた工程やリソースを、組織全体で横断的にサポートするのがPMOの特徴です。
たとえば進捗状況を可視化する仕組みを整えたり、リソースの調整を行ったりといった役割があります。
昨今、サービスやシステムが複雑化していくなかで、プロジェクトに関係するプレーヤーが過去とは比較にならないほど増えていく傾向にあり、一人のPMがプロジェクト全体をマネジメントするには限界があります。
このため、PMOはプロジェクトマネジメントの土台となる環境を整え、PMがプロジェクトの意思決定に集中できるよう支援する目的で設立されました。
つまりPMOは「プロジェクトを円滑に進めるための土台」を提供し、各PMが本来のリーダーシップに集中できるようにする存在といえるでしょう。
具体的には、プロジェクトに必要なリソースを調整したり、プロジェクト・マネジメント方式を構築したりすることで、円滑なプロジェクト推進を支援します。
PMOの主な役割

PMOは単なる管理部門ではなく、プロジェクトの成功率を高めるために多面的な役割を担っています。ここでは代表的な役割を3つに分けて解説します。
プロジェクト管理の標準化
企業が複数のプロジェクトを進める場合、プロジェクトごとに管理手法がバラバラだと、進捗や成果を比較するのが困難になります。
PMOは 標準的な管理プロセスやドキュメントのフォーマット を整備し、組織全体で一貫したマネジメントを可能にします。
これにより、経験の浅いPMでも一定の品質でプロジェクトを遂行でき、ナレッジの蓄積や横展開がしやすくなるのです。
プロジェクト進捗のモニタリング
PMOは各プロジェクトの進捗状況を俯瞰的に把握し、経営層やステークホルダーに報告する役割も担います。
進捗の遅れや課題が早期に発見できれば、迅速な対策が可能になります。
また、進捗データを分析することで「どのような要因が成功・失敗を左右したのか」を把握し、次のプロジェクト改善にも活かせます。
リソース最適化と調整
企業では限られた人材・予算・時間を複数のプロジェクトでシェアする必要があります。PMOは組織全体を見渡し、 リソースを最適に配分する調整役 として機能します。
例えば「Aプロジェクトが遅れているから優先度を上げて人員を追加する」「同じスキルを持つ人材を複数案件で重複してアサインしないようにする」といった対応が可能になります。
PMとの違い

役割の違い
プロジェクトマネージャー(PM) は、特定のプロジェクトを成功に導く「実行責任者」です。
計画を立て、チームを指揮し、期限・コスト・品質を守りながら成果物を完成させることが求められます。
言い換えると、PMは「個々の試合を勝ち抜く監督」のような存在です。
一方で、PMO(Project Management Office) は、特定、もしくは複数のプロジェクトを俯瞰的に見て、標準化・支援・監督を行う組織的な機能です。
個別の勝敗ではなく、組織全体としての「リーグ戦の勝率」を高めるために動きます。
つまりPMOは「クラブ全体を支える本部スタッフ」に近い立ち位置です。
権限と責任の違い
- PM
特定プロジェクトの成果責任を直接負います。納期遵守・予算内達成・顧客満足度などがKPIになります。意思決定権も強く、リーダーシップが求められます。 - PMO
→特定、もしくは複数プロジェクトを横断的に支援・管理します。責任は「個別プロジェクトの成否」だけではなく、「組織全体のプロジェクト成功率」を高めること意思決定権は相対的に弱く、標準化や調整、レポートによる影響力でプロジェクトを動かします。
業務範囲の違い
PMとPMOの業務範囲における違いは以下の表の通りとなります。
| PMの業務範囲 | PMOの業務範囲 |
|---|---|
| プロジェクト計画の策定 | プロジェクト管理手法の標準化 |
| チームメンバーの管理・指揮 | 特定、もしくは複数プロジェクトの進捗モニタリング |
| 進捗・品質・リスク管理 | リソースの横断的な最適化 |
| 顧客やステークホルダーへの対応 | プロジェクトマネージャーの教育・支援 |
両者は役割も責任範囲も異なりますが、互いに補完し合うことで最大の効果を発揮します。
もしPMとPMOの役割分担が曖昧だと、責任の押し付け合いや摩擦を生む可能性があります。
そのため、導入初期の段階で「PMは成果物の責任者」「PMOは成功環境の設計者」と明確に線引きすることが非常に重要です。
導入のメリットとデメリット

PMOを導入するメリットとデメリットにはを以下のようなものがあります。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| プロジェクト成功率の向上 | コストの増加 |
| 経営層への情報提供と意思決定の迅速化 | 現場からの反発 |
| リソースの最適配分 | 権限と役割の不明確さ |
| ナレッジの蓄積と活用 | 成果が短期的に見えにくい |
| ステークホルダーとの信頼関係構築 | 組織文化とのミスマッチ |
それぞれ詳しく解説していきます。
メリット
1. プロジェクト成功率の向上
最も大きなメリットは、プロジェクトの成功率を高められることです。
従来、各プロジェクトはマネージャー個人の力量に依存して進められてきました。
しかし、属人的な管理方法では「進め方が人によって違う」「成果物の品質にばらつきが出る」「情報共有が不十分」といった問題が避けられません。
PMOが導入されると、標準化された管理手法や共通フォーマットを全社で適用することが可能になります。
その結果、進捗の把握やリスク管理がスムーズになり、失敗要因を早期に発見できるようになります。
2. 経営層への情報提供と意思決定の迅速化
経営層が正しい判断を下すためには、全社的なプロジェクトの進捗やリスクを俯瞰的に把握する必要があります。
しかし、各プロジェクトがバラバラの形式で報告を上げていたのでは、全体像を把握するのに時間がかかり、意思決定が遅れてしまいます。
PMOはプロジェクト情報を統一フォーマットで集約し、ダッシュボード化することで「どのプロジェクトが遅れているか」「どこにリソースを追加すべきか」を一目で判断できる環境を作ります。
これにより経営層の意思決定スピードが向上し、事業戦略を柔軟に修正できるようになります。
3. リソースの最適配分
人材・予算・時間といったリソースは有限です。
複数のプロジェクトが同時進行する中で「優先度の高い案件に人を集中させる」「スキルが重複して配置されないよう調整する」といったリソース配分は、個々のPMには難しい判断です。
PMOは組織全体を俯瞰できる立場から、リソースの重複や不足を見極め、最適化を図ります。
たとえば「Aプロジェクトの遅延を解消するために、Bプロジェクトから一時的に人員をシフトする」といった戦略的な判断が可能になります。
4. ナレッジの蓄積と活用
PMOは各プロジェクトで得られた知見を蓄積し、次のプロジェクトに活かす「ナレッジマネジメント」の役割も担います。
成功要因や失敗要因を体系化し、教育や標準プロセスに反映させることで、組織全体の成熟度を高めることができます。
特に新任のPMにとっては、過去の知見が学習教材となり、即戦力化に繋がります。
5. ステークホルダーとの信頼関係構築
顧客や取引先にとって「進捗が見えないプロジェクト」は不安の種です。
PMOが導入されることで、透明性の高い報告が可能になり、ステークホルダーとの信頼関係を強化できます。
特に外部監査や規制対応が必要な業界(金融・製薬・公共事業など)では、PMOが品質保証の担保として機能します。
デメリット
1. コストの増加
PMOを設置するには専任の人材が必要であり、人件費やツール導入費用が発生します。
特に小規模企業にとっては大きな負担になる可能性があります。
また、PMOの価値を短期的に測定するのは難しく、経営層が「費用対効果が見えない」と判断すると撤退につながるリスクもあります。
2. 現場からの反発
PMOがルールや標準化を推進すると、現場のプロジェクトマネージャーやメンバーが「自由度が奪われた」「形式ばかり増えて実務がやりにくい」と感じることがあります。
過剰な管理や報告義務が増えれば、現場のモチベーション低下や形式的な対応につながりかねません。
PMOは「管理と支援のバランス」を誤らないことが重要です。
3. 権限と役割の不明確さ
PMOの設置初期によくある問題は、PMとPMOの役割分担が不明確になることです。
PMOがどこまでプロジェクトに介入するのか、最終的な意思決定権は誰にあるのかを明確にしないと、責任の押し付け合いや摩擦が生じます。
特に「PMOが口を出しすぎてPMの裁量が奪われた」と感じさせると、導入効果が逆に損なわれてしまいます。
4. 成果が短期的に見えにくい
PMOの導入効果は、中長期的に現れることが多いです。
標準化やナレッジ共有の仕組みが定着するには時間がかかり、「導入から数カ月で成果が出ない」と焦ってしまうと、PMOが形骸化してしまいます。
短期的にはむしろ「管理業務が増えた」と感じられるケースもあります。
5. 組織文化とのミスマッチ
柔軟性やスピード感を重視するベンチャー企業などでは、PMOのような統制的な仕組みが馴染まないこともあります。
こうした環境でPMOを導入すると「官僚的だ」と批判され、逆効果になることがあります。そのため、自社の文化や成熟度に合わせた導入戦略が求められます。
実務レベルでみたPMOとは(良し悪しの違い)

PMOについては少し認識が誤っていることがあり、多くの現場でPMO=事務局と誤解されています。
プロジェクトを構成するメンバには各々役割があり、クライアントと直接交渉する営業担当・システムを製造する開発担当・プロジェクト全体を統括するPMなど、みな具体的な目標と成果が見える担当です。
一方で、PMOはWBSの作成や進捗・品質・課題などの管理プロセス構築がありますが、プロジェクトにおける成果や貢献度が定量化されにくい担当です。
実際に現場レベルでみた時に、どんなPMOが評価されているのか、またどんなPMOが評価が低いのかを挙げてみます。
望ましいPMOの姿とは?
数週間放置されている課題を見つけては解決を促したり、進捗遅延の傾向をいち早く掴んで、PMへ報告するなどして、早期のうちにリスクを摘み取るように促します。
PMOは過去に経験してきたプロジェクトや、自身の中で体系化したリスクマネジメント基準に照らし合わせ、いまのプロジェクトがリスク許容度を超えていないか判断します。
このため、必要な資質は、まずコミュニケーションスキルです。
PMOには数多くのIT関連のプロジェクトでPMを経験してきた方も多いのですが、良いPMOの素養としては、プロジェクトメンバーやプロジェクトオーナーとコミュニケーションを取るのがうまいことが挙げられます。
聞き取り力も、伝える力も十分なPMO人材は、リスクの伝達など、センシティブなコミュニケーションも苦にせず、プロジェクトをスムーズに進めることができます。
コミュニケーション能力が高く、リスクの見極めをして伝えるべき人に伝えたら、PMOの役割はその主要な部分を全うしていると考えられます。
しかし、さらに評価の高いPMOは、プロジェクト経験が豊富です。
経験が豊富であれば、プロジェクトマネジメントだけでなく、ピープルマネジメントの面でも経営のニーズにこたえることができます。
プロジェクトとは、人の集まりなので、求心力がないとばらばらになりがちです。
そんな時、ピープルマネジメントも行えるクラスのPMOとなると、意見の取捨選択・とりまとめ、また、プロジェクトに対する不満を持っているメンバーの説得など、プロジェクトにゆがみが出る前に必要な手立てを講じることができます。
圧倒的な力量を持つPMOになると、マネジメントにプラスし、業務改善や、人の育成まで短期で行うスキルがあります。
たとえば外部のコンサルティング会社からPMOとして現場に入ると、社内にややもするとノウハウ形成などはできないまま「単に仕事をやって引きあげる」ことになってしまいがちです。
しかし、力量のあるメンバーに支えられたPMOによると、最終的には客観的に効率的な工程を社内で横展開できるよう仕向けるなど、中立・かつ高度なスキルを用いて適切な行動をとることができるのです。このノウハウを備えているPMOであれば、業務改善の目標を高い確率で達成できます。
日本能率協会グループのクロスオーバーでは、以下の資質を備えた専門家によるサービスを提供しています。
- 高度なコミュニケーションスキル
- 豊富なプロジェクト経験
- マネジメントに関する知見
- 業務改善に関するノウハウ
また、コンサルティングサービスは、日本能率協会グループの中立性を生かした内容であると同時に、高いサービス品質をクリアしているものです。
そのため、ここでご紹介した望ましいPMOの姿を実現できます。
望ましくないPMOの姿とは?
一方で、淡々と事務作業のように仕事しているPMOは評判が良いとはいえません。
そもそもPMOとは膨大な管理作業の上に成り立っているところがあります。
しかし、管理はプロジェクトの本質的なことではないので、当事者意識を持つこと、そして積極的にプロジェクトに関与することの方が重要です。
例えば、プロジェクトで管理する課題管理簿は大規模案件ともなると、毎週数十件もの新規課題が積み上がります。
このような状況では、課題の内容や現場の逼迫状況を考える余裕ががなくなるため、担当へ対応を強要したり、ルールを押し付けたりする傾向にあります。
この状態が続くとPMOがどんどん孤立していくので、プロジェクト推進のために必要な情報が集まらず、問題が顕在化するまでリスクを予兆できない傾向にあります。
一方で、これまではPMOの役割は事務作業というイメージが強かったので、プロジェクトによっては業務経験の乏しい方をPMOに据えることもあり、PMOは本当にプロジェクトに必要なのか?という理由でPMOが設置されないプロジェクトも多いです。
今後求められるPMO人材とは

PMOの役割はこれまで「プロジェクト管理の標準化」「進捗モニタリング」「リソース調整」が中心でした。
しかし、ビジネス環境が急速に変化する現代においては、それだけでは不十分です。
今後のPMO人材には、従来の管理能力に加えて、戦略的視点や柔軟な対応力がますます求められるようになります。
1. 戦略と現場をつなぐブリッジ力
経営層は「事業戦略」を描き、現場は「実務」を進めます。しかし両者の間にはしばしばギャップが生まれます。
今後のPMO人材には、経営目線で「どのプロジェクトが事業戦略に直結しているか」を理解しつつ、現場が動ける形に落とし込む力が不可欠です。
単なる管理担当者ではなく、経営と現場をつなぐ“戦略実行の推進者”としての役割が期待されます。
2. デジタルスキルとデータ活用力
プロジェクト管理ツールやBIツールを活用して進捗を可視化し、データに基づいた意思決定を行うことが標準になりつつあります。
今後のPMO人材は、ExcelやPowerPointだけでなく、Jira、Asana、Power BI、Tableau といったデジタルツールを使いこなし、定性的な経験だけでなく定量的な分析に基づいて提案できる力が求められます。
3. コミュニケーションとファシリテーション能力
PMOは直接プロジェクトを動かすわけではなく、PMや現場メンバーを支援・調整する立場です。
そのため、強制力だけに頼るのではなく、関係者を巻き込み、合意形成を促す力が必要です。
特にリモートワークやグローバルチームが一般化した現代では、オンライン会議でのファシリテーションスキルや異文化理解力も重視されます。
4. 変化に対応できるアジャイル思考
従来型のPMOはウォーターフォール型のプロジェクト管理に強みを持っていました。
しかし、今日のプロジェクトは不確実性が高く、変化に迅速に対応するアジャイル型の手法が主流になりつつあります。
今後のPMO人材は、アジャイルとウォーターフォールの両方に精通し、状況に応じて最適な手法を選べる柔軟性が求められます。
5. 人材育成とナレッジ共有の推進力
PMOの役割は単なる進捗管理だけではなく、組織の「プロジェクトマネジメント力」を底上げすることにもあります。
次世代のPMを育成し、過去のナレッジを体系化して共有することは、長期的に組織の競争力を高めるために必要な要素です。
今後のPMO人材には、教育者・メンターとしての役割も期待されます。
まとめ

『PMOとは』をテーマに、その意味と役割について紹介しました。
PMBOKをはじめとして、プロジェクトマネジメントの手法は体系化されているものの、実際のプロジェクトにおいて正しく活用するには、豊富なマネジメント経験とコミュニケーションスキルが必要となります。
PMOの役割を深く理解するほど、これからの社会に必要な役割を担っていることが分かります。
プロジェクトが高度化、複雑化する時代だからこそ、多くステークホルダーと協力関係を構築しながら、プロジェクトの成功に導くPMOの役割が再注目されています。